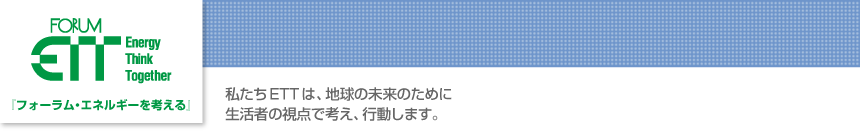
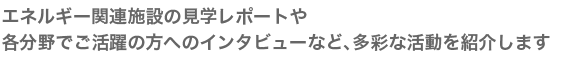


大正から昭和にかけて、日本では大規模な水力発電所が多く作られ、1950年代までは水力が電源別発電電力量において80%近くを占めていました。その後、高度経済成長により電力需要が急増したため、輸入化石燃料による火力、そして原子力へと燃料転換が行われてきました。社会情勢の変化に伴って電源構成も変遷してきましたが、水力発電は今、どのような役割を担っているのでしょうか?2013年11月20日、神津カンナ氏(ETT代表)が、長野県にある梓川水系を訪れ、水力発電の過去・現在を学びながら視察しました。
3,000m級の山々が連なる北アルプスにあり、日本で5番目に高い山、槍ヶ岳を水源とし、その南側に流れているのが、梓川です。梓川は山あいをつたって松本平に流れ、犀川、千曲川に合流しながら、やがて信濃川となって日本海に注いでいます。最上流の梓川は豊富な水量で昔から注目されており、大正末期から昭和初期にかけて8カ所の水力発電所が建設され、当時で10万kWの出力がありました。
 見学の前に、松本市内にある東京電力梓川総合制御所にて、説明を伺いました。現在、梓川水系には、ダム式・ダム水路式・水路式といった発電所方式を持つ10カ所の水力発電所があります。このうち、奈川渡(ながわど)、水殿(みどの)、稲核(いねこき)という3つのアーチダムの下には、ダム水路式の安曇(あずみ)、竜島(りゅうしま)、ダム式の水殿、稲核、という4つの発電所があります。一方、上高地の大正池を利用した霞沢(かすみざわ)のほか、湯川(ゆがわ)、沢渡(さわんど)、前川(まえかわ)、大白川(おおしらかわ)、島々谷(しましまだに)という6つの水路式発電所があります。梓川水系では昭和初期からこれまで、大規模な再開発が進められ、安曇、水殿、竜島の3つの発電所は1969年に新たに運転を開始、また既存の古い発電所についても改良により出力アップを図った結果、現在では梓川水系の合計出力は昭和初期当時の約10倍近い97万kWまで発電可能となっています。
見学の前に、松本市内にある東京電力梓川総合制御所にて、説明を伺いました。現在、梓川水系には、ダム式・ダム水路式・水路式といった発電所方式を持つ10カ所の水力発電所があります。このうち、奈川渡(ながわど)、水殿(みどの)、稲核(いねこき)という3つのアーチダムの下には、ダム水路式の安曇(あずみ)、竜島(りゅうしま)、ダム式の水殿、稲核、という4つの発電所があります。一方、上高地の大正池を利用した霞沢(かすみざわ)のほか、湯川(ゆがわ)、沢渡(さわんど)、前川(まえかわ)、大白川(おおしらかわ)、島々谷(しましまだに)という6つの水路式発電所があります。梓川水系では昭和初期からこれまで、大規模な再開発が進められ、安曇、水殿、竜島の3つの発電所は1969年に新たに運転を開始、また既存の古い発電所についても改良により出力アップを図った結果、現在では梓川水系の合計出力は昭和初期当時の約10倍近い97万kWまで発電可能となっています。
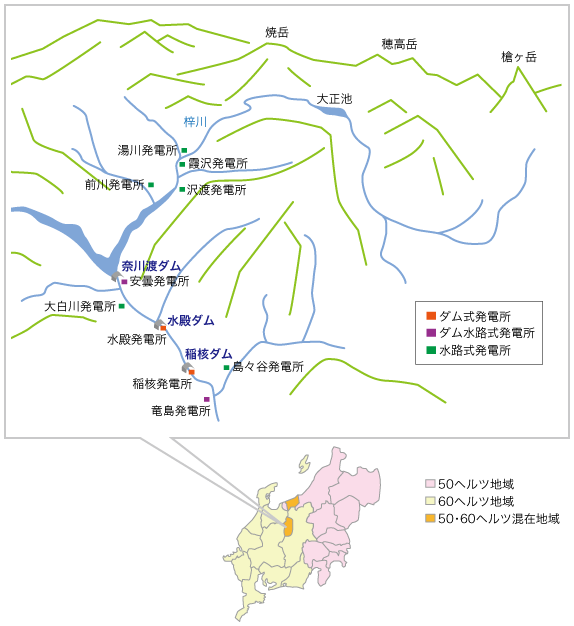
山間地にある発電所の設備点検や制御は、かつては3交替24時間監視を続けるため、運転保守担当の人員が常駐していましたが、ダム完成と制御機器の更新に伴い、奈川渡ダム右岸の梓川自動制御所からの遠隔操作によって管理されるようになりました。さらに水力発電の効率化を図るため、2009年に小諸市にある千曲川総合制御所において、長野県内4水系30カ所の発電所を集中監視制御するシステムが構築され、現在、各地にある発電所はすべて無人になっています。
梓川系水力発電所の特徴は、三つあります。一つ目は、東京電力霞沢発電所の電力は東京電力管内の山梨県に送られていますが、一部は隣接する中部電力霞沢変電所を経由して近隣の上高地などに中部電力が送電しています。本来、中部電力管内は周波数60ヘルツのところ、長野県のこの地域だけは50ヘルツになっているそうです。二つ目は、霞沢発電所から飛騨高山へ続く安房峠を越えて岐阜県にある北陸電力栃尾発電所まで、東京電力の送電線でつながっており、北陸電力と電気を融通することができます。北陸電力管内は60ヘルツですが、霞沢発電所の場合50ヘルツ、60ヘルツの両方で発電できるので、北陸電力を通じて同じ60ヘルツの関西電力への送電も可能になっています。そして三つ目の特徴は、奈川渡・水殿・稲核の3ダムの下流に、河川などから、かんがい用水を用水路に引き入れるための、農水省管轄のダム、梓川頭首工(とうしゅこう)があることです。梓川は急峻な河川であり、かつては、洪水による氾濫や日照りによる干ばつで農業用水の水量調整が大変でした。梓川の水量を一定にするため、ダム建設時に、東京電力が発電のために使った水を1万ヘクタールある松本平の農地に供給するための協定が取り交わされ、梓川頭首工のおかげで米や果樹といった農作物が盛んに作られるようになったそうです。
 車で標高1,500mの上高地へ向かうと、雪が舞い、凍るような寒さになっていました。夏には多くの人が訪れる人気の観光地である上高地の中でも、立ち枯れた木々が印象的な大正池は、1915年の焼岳の噴火により、流出した火山泥流が梓川をせき止めてできた自然の湖です。この大正池の水を引き入れ発電する霞沢発電所が1928年にできた当時、湖の総容量は約71万㎥ありました。ところが、上流域や焼岳から流入する土砂により、50年後の1976年には1/9の約8万㎥に減少してしまったのです。発電に必要な水量を確保するため、また大正池の景観保護を地元からも求められ、翌年から東京電力による浚渫工事が始まりました。
車で標高1,500mの上高地へ向かうと、雪が舞い、凍るような寒さになっていました。夏には多くの人が訪れる人気の観光地である上高地の中でも、立ち枯れた木々が印象的な大正池は、1915年の焼岳の噴火により、流出した火山泥流が梓川をせき止めてできた自然の湖です。この大正池の水を引き入れ発電する霞沢発電所が1928年にできた当時、湖の総容量は約71万㎥ありました。ところが、上流域や焼岳から流入する土砂により、50年後の1976年には1/9の約8万㎥に減少してしまったのです。発電に必要な水量を確保するため、また大正池の景観保護を地元からも求められ、翌年から東京電力による浚渫工事が始まりました。
 霞沢発電所に導水するために、大正池の水は通常、高さ約4.5mの一部ゴムでできたダム(ラバーダム)でせき止めてから取水していますが、台風、大雨などで河川が増水し水が濁った場合は、濁った水を使うと、発電用の水車の羽根が摩耗してしまうので、取水を止めてラバーダムの空気を抜くそうです。浚渫工事の手順としては、まず現地の工事現場で組み立てられ、大正池に浮かべられた幅6 m長さ25mの船に、水を吸い上げる大型ポンプを接続し、その先に取り付けた攪拌機(かくはんき)を湖の土砂の中に入れて、たまった土砂と水を一緒に吸い上げます。吸い上げられた土砂と水は導水管を通して「吹き上げ場」に運び、ここで沈殿した土砂から水を切り、ある程度、水分が除かれた土砂をダンプで運び出します。残った濁水は「沈殿池」に入れて、濁りを取ってから、大正池には戻さず霞沢発電所の取水口へ導水し、発電に使われた後に河川に放流しています。浚渫工事を始めるにあたり、社外の環境に関する専門家の方々と相談し、自然への影響が少ないと判断されたこの方法で、浚渫工事は今も続けられています。
霞沢発電所に導水するために、大正池の水は通常、高さ約4.5mの一部ゴムでできたダム(ラバーダム)でせき止めてから取水していますが、台風、大雨などで河川が増水し水が濁った場合は、濁った水を使うと、発電用の水車の羽根が摩耗してしまうので、取水を止めてラバーダムの空気を抜くそうです。浚渫工事の手順としては、まず現地の工事現場で組み立てられ、大正池に浮かべられた幅6 m長さ25mの船に、水を吸い上げる大型ポンプを接続し、その先に取り付けた攪拌機(かくはんき)を湖の土砂の中に入れて、たまった土砂と水を一緒に吸い上げます。吸い上げられた土砂と水は導水管を通して「吹き上げ場」に運び、ここで沈殿した土砂から水を切り、ある程度、水分が除かれた土砂をダンプで運び出します。残った濁水は「沈殿池」に入れて、濁りを取ってから、大正池には戻さず霞沢発電所の取水口へ導水し、発電に使われた後に河川に放流しています。浚渫工事を始めるにあたり、社外の環境に関する専門家の方々と相談し、自然への影響が少ないと判断されたこの方法で、浚渫工事は今も続けられています。
 毎年10月末に準備を始め、11月中旬から12月まで工事を行い、気温の低下による路面の凍結等、土砂を運び出すダンプの安全確保が厳しくなる1、2月は工事が中断されます。その後、寒さの和らぐ3月から土砂運搬が再開され、4月下旬まで行われます。浚渫工事が行われていることはあまり知られていませんが、その理由は、観光地である上高地の景観を守るため、4月下旬から始まる観光シーズンまでに、工事の形跡をすっかり消し去ってしまうからです。浚渫船を湖面に浮かべるためのスロープ、吹き上げ場、沈殿池といったすべての仮設備は、毎年、作業が終わると一度埋め戻し、また作業を始める時に掘り返しているのです。浚渫した土砂もすべて大正池の周囲から運び出されていますが、この土砂は、建設業などの用途でも使い切れない量があり、処理方法に困っているそうです。年間の浚渫量は1万8,000〜 2万㎥にも上りますが、浚渫工事を継続することで1976年当時の湖の容量を保っており、水力発電所としての機能維持と、観光地として人気のある大正池の景観維持の両面に貢献できるよう努めていきたいというお話でした。
毎年10月末に準備を始め、11月中旬から12月まで工事を行い、気温の低下による路面の凍結等、土砂を運び出すダンプの安全確保が厳しくなる1、2月は工事が中断されます。その後、寒さの和らぐ3月から土砂運搬が再開され、4月下旬まで行われます。浚渫工事が行われていることはあまり知られていませんが、その理由は、観光地である上高地の景観を守るため、4月下旬から始まる観光シーズンまでに、工事の形跡をすっかり消し去ってしまうからです。浚渫船を湖面に浮かべるためのスロープ、吹き上げ場、沈殿池といったすべての仮設備は、毎年、作業が終わると一度埋め戻し、また作業を始める時に掘り返しているのです。浚渫した土砂もすべて大正池の周囲から運び出されていますが、この土砂は、建設業などの用途でも使い切れない量があり、処理方法に困っているそうです。年間の浚渫量は1万8,000〜 2万㎥にも上りますが、浚渫工事を継続することで1976年当時の湖の容量を保っており、水力発電所としての機能維持と、観光地として人気のある大正池の景観維持の両面に貢献できるよう努めていきたいというお話でした。
 大正池から霞沢発電所まで車で降りてくると、標高のわずかな差で、天候は変わり薄日が差していました。建設から80年を超える建物は、当時の外観を保ち、窓ガラスの形などに懐かしさが感じられます。ドイツから輸入した水車と、レトロ感が漂うミントグリーンの小ぶりな発電機は、戦後になると日本のメーカーがメンテナンスを行うようになり、今も現役で動いています。発電の仕組みは、大正池からの取水を水路で導水し453mの落差を持つ水圧鉄管を通じて落下させ、その勢いでジェット噴射された水がバケットに当たって水車が回りその軸の回転により発電します。1台あたり13,000kWの最大出力を持つ発電機が3台あり、運転開始当時としては画期的な発電出力でした。外に出ると、説明で伺ったように中部電力と融通できる送電線が見えました。
大正池から霞沢発電所まで車で降りてくると、標高のわずかな差で、天候は変わり薄日が差していました。建設から80年を超える建物は、当時の外観を保ち、窓ガラスの形などに懐かしさが感じられます。ドイツから輸入した水車と、レトロ感が漂うミントグリーンの小ぶりな発電機は、戦後になると日本のメーカーがメンテナンスを行うようになり、今も現役で動いています。発電の仕組みは、大正池からの取水を水路で導水し453mの落差を持つ水圧鉄管を通じて落下させ、その勢いでジェット噴射された水がバケットに当たって水車が回りその軸の回転により発電します。1台あたり13,000kWの最大出力を持つ発電機が3台あり、運転開始当時としては画期的な発電出力でした。外に出ると、説明で伺ったように中部電力と融通できる送電線が見えました。 そして、もし仮に2本の送電線に事故があった場合でも、霞沢発電所からケーブルで直接、中部電力の変電所につながるルートがあり、バックアップ体制も万全だというお話でした。それぞれの地域と電力会社が複雑に入り組みながらも、互いに融通できる工夫がされているということを、変電設備や送電線を実際に目にすることで実感することができました。
そして、もし仮に2本の送電線に事故があった場合でも、霞沢発電所からケーブルで直接、中部電力の変電所につながるルートがあり、バックアップ体制も万全だというお話でした。それぞれの地域と電力会社が複雑に入り組みながらも、互いに融通できる工夫がされているということを、変電設備や送電線を実際に目にすることで実感することができました。
最後に、さらに下流にある奈川渡ダムを見学しました。堤の長さは約356mあり、貯水してあるダムの背面から底をのぞくと、150mの高さに目まいがしそうでした。このダムの総貯水量は、東京ドーム100杯分に相当する1億2,300万㎥。ダムの直下にある安曇発電所は、合計6台の発電機による総出力量が約62万kWですが、そのうち3〜6号機は、揚水式発電になっており、夜、火力発電などを使って下部ダムから上部ダムへ水をくみ上げておき、電力使用が多い昼に、その水を使って発電するという方法を取っています。
 今回の視察では、私たち日本人が、自然の恵みである山や水をいかにして上手に無駄なく使うための工夫をしてきたかを知り、また、北アルプスの深い山々で、厳しい冬も継続して行われている点検やメンテナンス作業によって、安定した電気がつくられ、送られてくるありがたみも併せて感じることができました。そして、自然の水からできた電気を使う、だから、大正池浚渫工事のように、今度は人が自然を元の姿に戻すようにする ── 人と自然との循環サイクルの継続こそ大切なのではないかと考えさせられました。
今回の視察では、私たち日本人が、自然の恵みである山や水をいかにして上手に無駄なく使うための工夫をしてきたかを知り、また、北アルプスの深い山々で、厳しい冬も継続して行われている点検やメンテナンス作業によって、安定した電気がつくられ、送られてくるありがたみも併せて感じることができました。そして、自然の水からできた電気を使う、だから、大正池浚渫工事のように、今度は人が自然を元の姿に戻すようにする ── 人と自然との循環サイクルの継続こそ大切なのではないかと考えさせられました。
「水力発電は自然との闘い」と教えてくれた人がいる。 河川の流れを人工的に引き込んだり、ダムや調整池に貯めた水の落差を利用して電気をつくり出す水力発電は、大自然の真っ只中で、人間がコントロールしきれない現象に常に向き合いながら営まれているのだと。 浚渫作業が繰り返し行われている大正池と、その水を源とする霞沢発電所を見学した時、私は、この「自然との闘い」がどういうものなのか、まざまざと思い知らされた。 源流域から土砂・岩石や倒木が水の流れに乗って運ばれてくるのも、ダムを取り囲む山々が絶え間なく崩れて砂が堆積していくのも、大雨や雪解け水による増水も、日照り続きによる渇水も、紛れもなくすべて自然の営みであり、それは、時として牙をむき出すようにして、人間に襲いかかってくることさえある。 しかし、水力発電の現場に身を置いた時、自由奔放な自然の振る舞いに翻弄されながらも、その営みをありのままに受け入れ、それと共存しながら大自然の叡智に懸命に立ち向かっている人間の姿を目の当たりにした。 自然の営みを人間の都合に従属させるために、刃を突き合わせて自然と対峙し格闘しているのではないのだ。 北アルプスの麓、凍てつくような寒さの中で、「自然との闘い」の本当の意味を肌で感じ、こうべの垂れる思いであった。
神津 カンナ