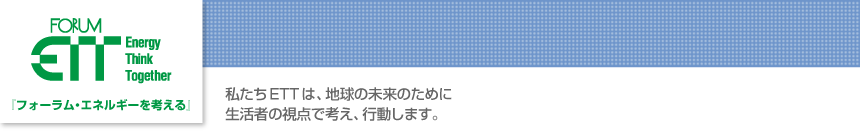

初夏の英国に来ている。専門家へのインタビューや、余暇に訪ねた友人宅での会話を通じて今回強く感じたことは、エネルギー問題をどう捉えるかは、各国の気候や資源の有無、人口の多寡や産業構造のみならず、その国の歴史を含めた“国民性”の一部であるということだ。
フランス、オランダと国際連系線を有しているものの、我が国同様島国であるイギリスでは、エネルギーの安定確保に対する意識は、他のヨーロッパ諸国と比較しても格段に高い。ロシアの天然ガスへの依存を極力避けることは、当然国民的コンセンサスとして作用し、北海油田が枯渇しつつあることもその傾向に拍車をかけている。
また、厳しく長い冬は、いわゆる「energy poor」と呼ばれる低所得者層にとってはまさに死活問題であり、電力料金に関する国民の関心も高い。しかし実はイギリスでは、1990年の電力自由化導入後、数年は価格の低下傾向が見られたがその後大きく上昇、2003年と2010年で比較すると、家庭用電気料金は1.8倍にも上昇している。しかも3ヶ月ごとの請求システムになっているそうで、友人は「3ヶ月に一度悪魔が来る」と表現した。イギリスにおける電力料金上昇は、燃料価格高騰、環境対策、再生可能エネルギー促進費用など複合的原因によると言われているが、自由化・規制緩和により事業者が価格転嫁しやすい構造であることが根本的に作用している。自由化は誰を自由にするのか、という問に対して日本においては消費者の選択の自由が増えることのみ強調する報道が多いが、自由化は事業者と消費者双方を自由にするものなのだ。
しかし、イギリス国民が電力市場の自由化を悔いているかといえばそうでもないようだ。電気は確かに公共性が強いが、あくまでも普通の商品であり、自分たちが「選択して買える」ことが重要らしい。
国民がエネルギー問題をどう捉えているか、それはその国の歴史や国民の思考回路を知る上で非常に面白いテーマである。はて、我が日本人の“国民性”をどう説明したものか。「これまで一部の方々を除いてあまり考えて来なかった」とは言いたくないのだが・・。
(2013 年7 月末)